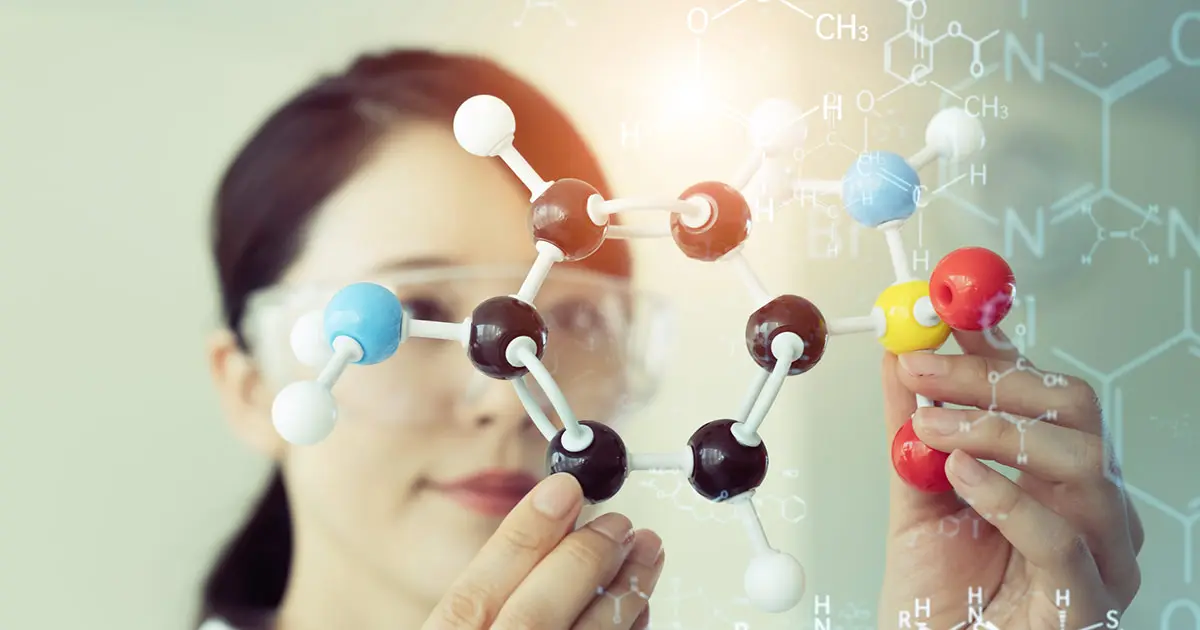監視はイヤvs支援はいる…Z世代が抱く抑圧的管理への嫌悪と改善

マイクロマネージメントの真のメリットについては、連載初回の記事で紹介しました。一方、デメリットとしては、大きく2つの懸念があります。それが、「過度な監視や干渉の影響」と「不十分なフィードバック」。
これはZ世代で特に顕著に見られる感覚です。デジタル・デバイスやツールと親和性が高い世代の視点から、今一度、この点を見てみましょう。これは、この後の記事へと続く伏線でもあります。前後の記事と併せてお読みください。
逆効果!? マイクロマネージメントのデメリット
いくらメリットがあっても、マイクロマネージメントに対する反応は、個人の価値観や経験、職場環境によって大きく異なります。過度な監視や干渉は、無意味などころか逆効果。
Z世代(1997〜2012年生まれ)は、デジタル・ネイティブとして知られ、2000年代以降の生まれはソーシャル・ネイティブでもあります。彼らは、コミュニケーションやワーク・スタイルにおいても独自の特性を持っています。この世代は特に、職場での過度な監視や細かい指示に対して反発する傾向があり、マイクロマネージメントのデメリットを整理する上で有効です。
過度な監視や干渉による悪影響
ストレスと不満:過度な監視は従業員にストレスを与え、仕事に対する不満を引き起こすだけ。Z世代は、従来のオフィス文化よりもリモートワークやフレックスタイムなど、柔軟な働き方を好む傾向があります。自由度や自主性を重視し、過度な管理や監視に対して閉塞感を感じることが多いとされています。
エンゲージメントの低下:監視社会の象徴として使われる「パノプティコン」のような、見られている感覚そのものに不安や不快感を覚え、ネガティブな心理的反応が生まれます。従業員が自分の業務を自分で管理している実感を持てない場合、エンゲージメントが低下し、生産性の低下や組織リスクに。
イノベーションの障害:指示通りの業務遂行やミスのない過去のリピートなら、むしろAIが得意。従業員の意欲が削られることは、過去の学習からは生まれない自由な発想による、革新的アイデアの創出の阻害に。
プライバシーの侵害リスク:収集した細かなデータが適切に管理されない場合、個人情報の漏洩や不正利用のリスクに。企業をターゲットに、従業員が狙われる事件も多数発生。
適切なマネージメントがないことの不安
世代ごとの意識の違いは、国境や人種を越えることがあります。Deloitteは2024年、44カ国23,000人以上のZ世代とミレニアル世代(1981~1996年頃生まれ)を対象にした調査結果を発表しました。
このレポートに依ると、1/3が経済状況の好転を期待していて、その背景には自身の金銭面の不安と社会の不安定があります。彼らは、仕事の目的を重視し生成AIの関心も高い一方で、失職への懸念からスキルアップとトレーニングを意識しています。また、環境負荷や格差、メンタルヘルスへの意識も高く、自分の倫理観や価値観に合わない仕事は拒絶する傾向にあります。
成長ニーズを無視:働く目的意識や意欲が高く成長や学びを重視する若年層は、自信を持って業務に取り組みたい。チャレンジはしたいが失敗も怖いので、前例を知りたい。
メンターシップの欠如:必要な指導やアドバイス、適切なメンターシップやコーチングがないと、スキル向上やキャリア形成にとってもマイナス。次のチャンスの損失に。
妥当な監視と適切な支援は、全く矛盾しない!
確かに一部の人々は、過度に細かく監視されることに嫌悪を感じ、明示的・暗示的に取得されるデータの管理にも警戒心を抱いています。その一方で、管理者からの指導やサポートがないと、「自分はうまくやれていないのではないか?」という不安を感じやすい傾向があります。
仕事なので仕方なく従ってはいるものの、目的や用途、制限など、信頼関係が十分に構築されていないうちに、マネージメントと称して細かく監視されることの心理的警戒感。高く信頼されているので敢えて声を掛けられていないのか、それとも、諦められ無視されているだけか、自分では分からない不安…
監視されるのはイヤだが、支援はしてほしい—この二つの感覚は、一見、矛盾しているように思えるかもしれません。しかし、どちらか一方しか選べないトレードオフではなく、「適切な管理とフィードバックのバランス」は実現可能です。これはZ世代に限ったことではありません。
▼部下の成長支援を目的とした1on1ミーティングに関する定量調査 – 株式会社パーソル総合研究所 シンクタンク本部
https://rc.persol-group.co.jp/thinktank/assets/1on1.pdf
意義あるマイクロマネージメントの運用とは?
結局、何の・誰のための管理か?という合意形成が鍵。マイクロマネージメントが受け入れられるには、以下のような点が重要です。
企業文化の醸成
システムや体制も重要ですが、そもそも、マイクロマネージメントが受け入れられやすいかどうかは、組織のカルチャーが大きく影響します。
オープンで協力的、アジャイルな文化があれば、データを活用したマネージメントが効果的に機能します。逆に閉鎖的だと、根強い抵抗も。つまり、文化の醸成には時間も手間も必要。
過度な監視の回避
日本の企業文化では、個々のプライバシーや自由が重視されず、特に上司からの過度な干渉や監視が不快に感じられることも多いもの。過度な介入を避け、信頼と自主性のバランスを保つには、監視ではなく支援としての管理、透明性ある仕組みが必須です。
心理的安全性の確保
得られるデータは、あくまで数値や指標。1on1など、従業員との対話を通じて感情や意見を理解し、データに表れない細部を補完することが重要です。
コミュニケーションの目的は、心理的安全性の確保による上司と部下の良好な関係づくり。そのためには、部下から上司へ自由に意見を言える環境を整え、過度な監視と受け取られない信頼関係が求められます。
データの解釈と活用
膨大なデータを収集したところで、それを正しく解釈し、意味のある情報に変換するのは人間の役割。背後にある文脈(コンテキスト)や従業員の個別の状況を理解することが重要です。
上司からは、適切なタイミングと質のフィードバックもポイント。具体的な目標設定や建設的な意見、定期的な評価によって、メンバーの成長をサポートし、不安や不満を解消できます。
適切なフレームワークの併用
自己管理を促進するフレームワークとして、OKRも知られています。目標(Objectives)と主要な結果(Key Results)の2つの要素で作られ、自主性を尊重しつつも、適切なフィードバックやサポートを提供する方法です。自社に合った、目標設定に基づく管理を強化することも有効です。
マネージメント側のスキル
収集したデータを効果的に活用し、メンバーそれぞれの活動をサポートするには、マネージャー自身が分析やフィードバックの技術を学ぶ必要があります。トレーニングを通じてマネージャーがスキルを身につけることで初めて、メンバーの成長を支援できます。
ウェアラブルデバイスの活用
GarminやFitbit、Apple Watchなど、IoTとしてのウェアラブルデバイスから得られる細かなデータが、健康増進と仕事に役立っています。詳しくは、次回の記事で!
前回と今回の記事では、マイクロマネージメントに対する文化や世代、年齢の違いを踏まえた、テクノロジーによる新しいアプローチにフォーカスを当てました。
ただし、いくつかの属性だけで個人を判断するのは乱暴です。特定のクラスターをそのままアイデンティティーと雑に結びつけると、個別のニーズや傾向を見落とします。例えば、Z世代の一部には、自由や自律性ではなく、権力を持った独裁者による統治を望む声があります。
その一方で、やはり抑圧的な監視は警戒される傾向は強いので、個人ごとの思考や好みを反映させるには、結局、細かなチェックによる実践的・具体的なアプローチが必要なはず…という堂々巡り。
では、マイクロマネージメントという単語を、例えば「パーソナライズのためのモニタリング」や「自分を次のステップへと導くサポートとフィードバック」と言い換えるとどうでしょう?印象はかなり変わりそうです。ング」や「自分を次のステップへと導くサポートとフィードバック」と言い換えるとどうでしょう?印象はかなり変わりそうです。
さて、モニターやサポート、フィードバックといえば、前述のようなウェアラブルデバイスは、個人のスポーツや健康管理に使われています。もちろん、Z世代にも広く人気。実はこれが、従業員の健康管理や作業効率のアップにも導入されています。次回は、そんなIoTデバイスを使ったマイクロマネージメントの実例を見てみましょう。
Z世代の当事者も、Z世代と仕事をしている皆さんも、ぜひご感想やご意見をお聞かせください。