ローコンテキストvsハイコンテキスト、両者の違いや特徴を知る

グローバル化とリモートワークの普及によって、遠隔地とのコミュニケーションのあり方に大きな変化がありました。そこで改めて注目されるようになったのが、ローコンテキスト(低文脈)なコミュニケーションです。特に、日本のようなハイコンテキスト(高文脈)社会では、両者の違いやそれぞれの特徴、注意点を意識しておくことが重要です。今回は、コンテキスト(コンテクスト)とはそもそも何なのか、ローコンテキストとハイコンテキストはそれぞれどんな特徴があるのか、基礎を知ってみましょう。
コンテキストとコンテンツとの関係って?
まずは、用語の分解と整理から。コンテキストまたはコンテクスト(context)とは、文脈や状況、前後関係、背景、繋がりのことです。そして、コンテキストとセットで語られることが多いのが、コンテント(content)—複数ならコンテンツです。この言葉が指すのは、中身や情報、出来事です。文章や写真、イラストレーション、音楽、音声、ビデオ、映画、本なども、コンテンツとして認識されています。こちらは、2000年代に入ってすっかり定着しましたね。
コンテキストとコンテンツを比較・整理すると、こういう考え方ができます。ソーシャルメディアなどで、前後の文脈を無視して情報の一部だけが切り取られると誤解を生んでしまうのは、ある意味当然と言えます。
コンテキスト:
- 文脈や状況、前後関係、背景、繋がり、入れ物
- 重要なのは、誰がどんな状況で言ったか
コンテンツ:
- 中身や情報、出来事
- 重要なのは、何が語られたり、入っているか
ローコンテキストとハイコンテキストという概念は、人類学者のエドワード・T・ホールが1959年に出版した『The Silent Language(邦題:沈黙のことば)』で初めて紹介されました。コンテキストがロー(low)であるというのは、複雑な文脈を前提にせず、シンプルであるということです。逆に、文脈が複雑化・高度化し、分かる人たちだけが分かる共通概念をベースにしたコミュニケーションは、ハイ(high)コンテキストです。2つのコミュニケーション手法は、文化的な性格や、明示と間接の程度が違います。それぞれの特徴を見てみましょう。
コミュニケーションにおける、コンテキストのローとハイとは?
ローコンテキストなコミュニケーションで重要なのは、発言することです。情報は、明確に言語化して伝える必要があります。言葉に基づいているため、沈黙は断絶であり、不安を抱かせます。論理的な意志決定が重視され、変更は容易ではありません。
ローコンテキストなコミュニケーション
- 直接的で明示的な言葉を重視し、話す言葉に重点を置く。
- 仕事とプライベートの区別がはっきりしていて、個人主義、タスク志向の傾向が強い。
- コミュニケーションにおいて明確さと正確さを重視し、事実やデータ、論理に基づいて情報を伝達する。
- 意味を伝えるために明確な言葉や表現を使い、コミュニケーションスタイルが対立的または自己主張的である。
- ドイツ系スイスやスカンジナビア、アメリカ、フランスなどの文化圏が顕著。
一方、ハイコンテキストなコミュニケーションで重要なのは、察知することです。情報は、言語以外の文脈も重要で、言語化も曖昧です。共通認識に依存しているため、沈黙は必ずしも不快ではありません。感情的な意志決定が重視され、状況で柔軟に変更されます。
ハイコンテキストなコミュニケーション
- 調和と間接的なコミュニケーションを大切にし、人間関係の構築と維持に重点を置く。
- ボディランゲージや声のトーン、文脈など、非言語的な手がかりをより重視して意味を伝える。
- 集団主義的で人間関係を重視し、仕事とプライベートの境界が曖昧になる傾向がある。
- 意味を伝えるために、微妙な表現や間接的な言葉を使うことがある。また、対立や直接的な意見の相違を避けることがある。
- 日本や中国、アラビア諸国、ラテンアメリカ、アメリカ先住民族などで顕著。
ローコンテキストとハイコンテキストコミュニケーションの長所と短所
ローコンテキストとハイコンテキストな文化や思考が衝突すると、当然、ディスコミュニケーションが起きます。前後の文脈を無視して、直接的過ぎる言い方をすれば、『口の利き方を知らない失礼な言い方だ!』『何でもずけずけ言えばいいってもんじゃないのに…』というリアクションが返ってくるでしょう。逆に、身内同士でしか伝わらない表現で、記録にも残さなければ、『それぐらいのこと、ちゃんと察して動け!』『そんなつもりで言ったわけじゃなかったのに!』といった、これも余計な感情論になってしまいがちです。
そんな、ローコンテキストとハイコンテキストコミュニケーションの長所と短所を整理してみましょう。ただし、これらは普遍的なものではなく、特定の文化的背景や個人の資質によって異なる可能性があることは、留意しておく必要があります。
ローコンテキストコミュニケーション
| 長所 | 短所 |
|---|---|
| 明確・正確 | 攻撃的、無神経と思われる可能性がある |
| 直接的・明示的 | 文化的な違いに柔軟に対応できない |
| より対立的 | ニュアンスや繊細さに欠けることがある |
| 長所 | 短所 |
|---|---|
| 明確・正確 | 攻撃的、無神経と思われる可能性がある |
| 直接的・明示的 | 文化的な違いに柔軟に対応できない |
| より対立的 | ニュアンスや繊細さに欠けることがある |
ハイコンテキストコミュニケーション
| 長所 | 短所 |
|---|---|
| 人間関係の構築と維持 | 間接的、あいまいと思われる可能性がある |
| 非言語的な手がかりや文脈に依存 | 非言語的な合図を理解・解釈するために、より多くの努力が必要 |
| 直接対決を避ける | 文脈が共有・理解されていない場合、誤解を招くことがある |
| 長所 | 短所 |
|---|---|
| 人間関係の構築と維持 | 間接的、あいまいと思われる可能性がある |
| 非言語的な手がかりや文脈に依存 | 非言語的な合図を理解・解釈するために、より多くの努力が必要 |
| 直接対決を避ける | 文脈が共有・理解されていない場合、誤解を招くことがある |
ハイコンテキストな日本社会と労働環境
次に、自分が働く周囲の環境を見渡してみましょう。日本社会ならではの文化的特徴や伝統は、一部で今も受け継がれています。
グループ志向:日本社会は、集団の調和と合意形成に重きを置いています。伝統を重んじることは、素晴らしい面もありますが、業界や組織の規模、職場環境によっては、今でも封建的な年功序列の階層構造になっていることが多く見られます。これは、職場の肩書きや呼称、同調圧力を感じさせるカルチャーなどにも表れています。
非効率な長労働時間:OECDデータに基づく2020年の日本の時間当たり労働生産性(就業1時間当たりの付加価値)は、49.5ドル(5,086円/購買力平価換算)で、OECD加盟38カ国中23位に留まっています。労働者は長時間労働が多く、生産性よりもとにかくオフィスにいることが重要視される「プレゼンティズム」の文化があります。
同質的コミュニティー:ソーシャルメディアで時々、地方移住者の厳しい現実が話題になっています。人々が同じような外見で、同じ言語を使い、同じような価値観で生活しているコミュニティーは、異質な存在をはっきりと拒絶しないまでも、ひっそりと穏やかに排除していきます。難民の受け入れ率の低さや、技能実習制度の人権問題も無関係ではないでしょう。
ハイコンテキストな社会:今回のテーマがまさにこれ。日本は、世界的に見ても特にハイコンテキストコミュニケーション(高密度な文脈)社会であることが知られています。前述の3つの特徴すべてにおいて、通じ合っている相手にだけ分かればいい、非言語的な合図や文脈情報が重視されます。
今回はまず、コミュニケーションにおけるローコンテキストとハイコンテキストという、文脈の扱い方に2種類の手法があることをご紹介しました。ではこれらを私たちはどのように使い分ければいいのか、次回、さらに考えてみましょう。




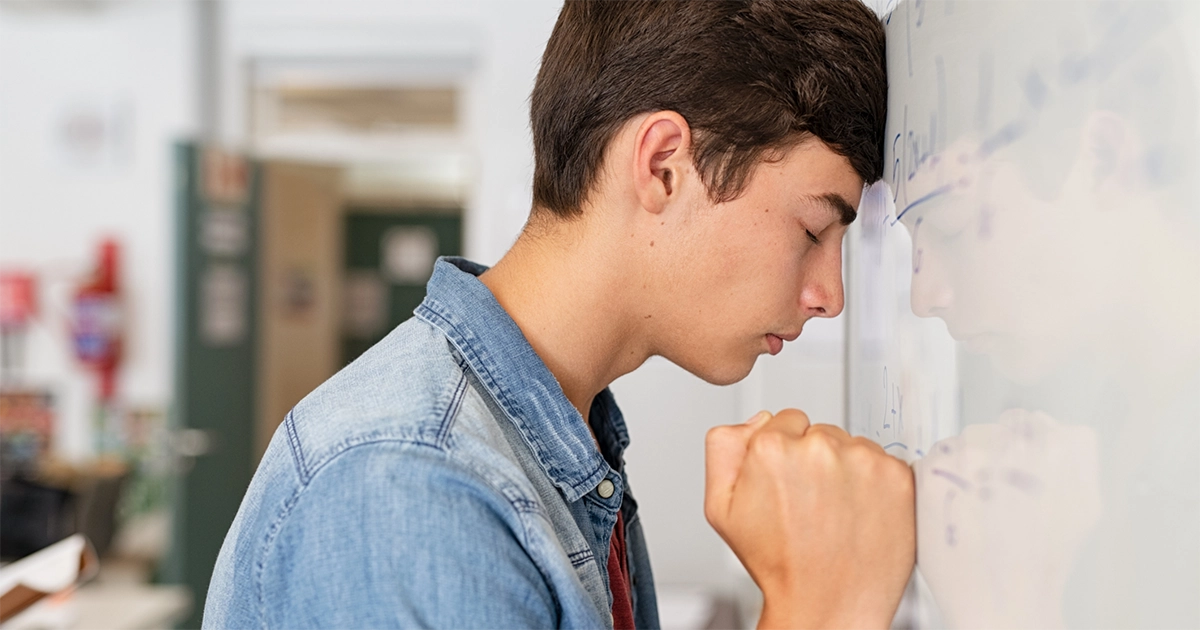




四葉さん、コメントいただきありがとうございます。にんじんです。 僕がこの会社この…
面白い話をありがとうございます。私自身は法学部ですが哲学にも興味があります。 ふ…
要所要所に別記事が挿入されていて読みやすかったです! 文系の人でもバイオインフォ…
お読みいただきありがとうございました。最果タヒさんの作品は、詩集だけでなくエッセ…
萩原朔太郎や宮沢賢治の詩集が好きなのですが、同じ読書という行為であっても小説を読…