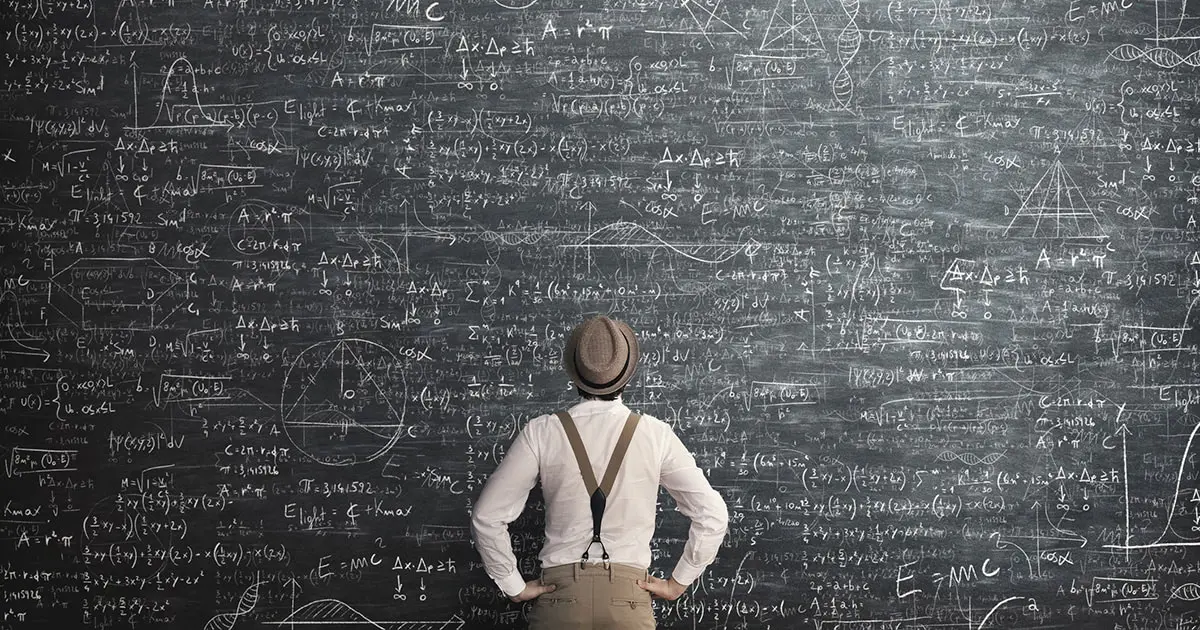宇宙はちょっと遠くても、自動化と遠隔操作は誰にでも身近な世界

早稲田大学ビジネススクール教授として、いろいろなメディアで知られている入山章栄さんが、架空のカフェのマスターになり、毎回いろいろな常連客やゲストを迎えてトークする「浜松町Innovation Culture Cafe」。文化放送で毎週月曜日19:00から放送されている、人気のラジオ番組です。アシスタント店員は、ITベンチャーの広報も務めるタレントの田ケ原恵美さんです。
この「浜カフェ」に先日、2週連続で来店していたのが、一般社団法人SPACETIDE 代表理事兼CEOの石田真康さんと、株式会社ジザイエ 代表取締役CEOの中川純希さんでした。この時、取り上げられていた、宇宙と建設現場における自動化と遠隔操作のトークがとても興味深かったので、リープリーパー視点でいろいろ考えてみました。
なお、この番組はPodcastとしても配信されているので、好きなプラットフォームで聞いてみてください。
世界的に宇宙ビジネスは活況なものの
石田さんのSPACETIDEは、日本初の民間宇宙ビジネスカンファレンスの運営を手がける企業で、宇宙ビジネスの新しい潮流を作るということをミッションにしています。
現在、世界全体で宇宙産業への注目が高まっていて、専用のファンドも活況なほど資金集めは比較的スムーズのようです。ロケットの打ち上げや衛星の開発など、アメリカやロシア、中国、EUなどが先行し、日進月歩の技術革新が起きていて、中国やインドのチームが月のミッションに成功しています。日本チームも、果敢にチャレンジを続けています。
しかし、ここでもやはりエンジニア不足が深刻とのこと。また、ウクライナ危機もあり、衛星データと安全保障の関係にも触れられていました(放送後に起きた中東情勢も、何らかの影響は必至)。また、後発組の日本は、衛星を使ってどういうサービスを提供するか、違う価値を提供しなければ生き残れないだろうという、シビアな話も出ていました。
人間ならではの活動と、通信遅延という問題
宇宙は、遠隔操作よりも基本は自動化がメインという話で、ロケットの打ち上げや月に向かう探査機、衛星だと普段の運用なども自動航行とのことでした。月への着陸指令を出したり、メンテナンスや検査はリモートで操作されています。例えば宇宙ホテルなど、人類が一定期間居住する生活施設の建設も遠い夢物語ではなさそうです。
限られた人数と時間しかない中で、多数のミッションをこなさなければならない宇宙飛行士の時間は貴重です。そのため、人間でなければできない付加価値の高い作業に集中するために、最近ではロボットアームの操作は、地上からの遠隔操作に切り替わっているそうです。
ただ、宇宙は通信の遅延が非常に大きいことが課題として挙げられていました。地球から月の距離が38万km。光のスピード約30万kmだと往復で大体2.6秒ぐらい遅延し、信号処理でさらに数秒掛かってしまう。これが、火星だと最大40分にもなる。物理的限界があるので、どうしても通信のスピードが出ず、安定しない。
そんな通信も含め、総合的な技術が求められるのが遠隔操作だという話でした。通信プロトコルの設計やロボットアームの動作、人間が操作しやすいUI、感触フィードバックなど、自動化より難しいものの、ニッチな領域に可能性があるという希望が語られていました。
自動化を目指す国々と、遠隔操作にも拘りたい日本
非常に興味深かったのは、自動化と遠隔操作の考え方について、国家間で差があるという話でした。アメリカや中国は、AIやロボットで自動化・自律化が前提で、人の関与を極限まで減らす概念な一方、日本はむしろ遠隔操作を重要視しているとのこと。ここでも、マンガやSF文化の影響が見られるようです。
例えば、航空機の設計思想にしても、緊急事態が起きた時に機体の自己判断に任せるのか?それとも最後は人が判断する機能を残すのか?最終的な責任の所在は誰が負うのか?これは、エンジニアリングの話というより、倫理的・哲学的・法学的な話の領域です。
また、自動車は元々、前進・後退でギアを切り替える必要がありました。それが自動運転車になるとボタン式の電気信号に変わりました。しかし、人間としてのドライバーも操作することを意識すれば、メカニカルな動きを残す必要があります。この両者を高いレベルで融合することが如何に難しいことか、素人でも想像がつきます。
『確かに、自律的に動かすのは技術で可能だが、人として感動がない』という話を聞いたとき、『ChatGPTは驚くほど優秀なプログラムを書けるが、コードをゴリゴリ手で書いていく楽しさが感じられない』という、エンジニアの書き込みを思い出しながら聞いていました。この辺りは、仮想労働者であるデジタルレイバーが、下僕なのか、コパイロット(副操縦士)なのかという意識の違いも想起させました。
自分が遠隔操作している感覚にとって重要な0.7秒
石田さんは、『宇宙で今までやってきたのは、遠隔操作ではなく遠隔指令だった』という話をされました。衛星の切り離しや着陸、分析など、確かに、全ては一方的な指令です。それに対して遠隔操作は、指令を出す側自身が、自分が操作している感覚が重要です。
ただし、『人間は、反応が0.7秒以上遅れると自分が操作している感覚がなくなる』という研究があるそうです。そこで、人が遅延を違和感として感じないようにxR(AR 拡張現実/VR 仮想現実/MR 複合現実)技術で補える、UI(ユーザーインターフェース)やUX(ユーザー体験)の可能性が言及されていました。また、メタバースの仮装体験や、自分が地球からローバーやロボットを運転できるような、エンターテインメントとしての可能性もありそうです。
『スター・ウォーズ』と『マトリックス』の世代による意識の違い
宇宙絡みの架空のストーリーが、現実とシンクロする話も面白く聞きました。『スター・ウォーズ』世代が機体に乗って体を張ることに永遠のロマンを感じる一方で、『マトリックス』世代は完全なものを再現すればいいと考えるという、世代間の意識の違いがあるのだそうです。やはり、近未来をリアルに想定して物語を描き、現在を逆算して考えるSFプロトタイピングは、本物の現場でも有効のようです。
これは、一般企業でも『やはり現場で顔を合わせなければ』派と、『すでに現場こそがオンラインである』派のズレがあることにも通じています。映画『スター・ウォーズ エピソード4/新たなる希望』公開から46年、最初の『マトリックス』公開から24年が経過していますから、そろそろ次の世界観のモデルがあってもよさそうですね。
地理的・物理的にそこへ簡単に行くことはできないものの、何かを判断する必要がある。これは決して近未来の話ではなく、リモートワークで私たちが日々経験していることです。コミュニケーションと意志決定の難しさもあって、アフターコロナの働き方として、一部の企業では出社への回帰や、出社とリモートのハイブリッドなワークスタイルが普及しつつあります。ビデオ会議プラットフォームのZoomですら、従業員に出社を求めて話題になりました。
しかし、リモートワークができる職業は限られています。DX人材不足や教育という課題もあります。それを解決するジザイエ中川さんの「自在化身体」「遠隔就労プラットフォーム」の話は、また次回!