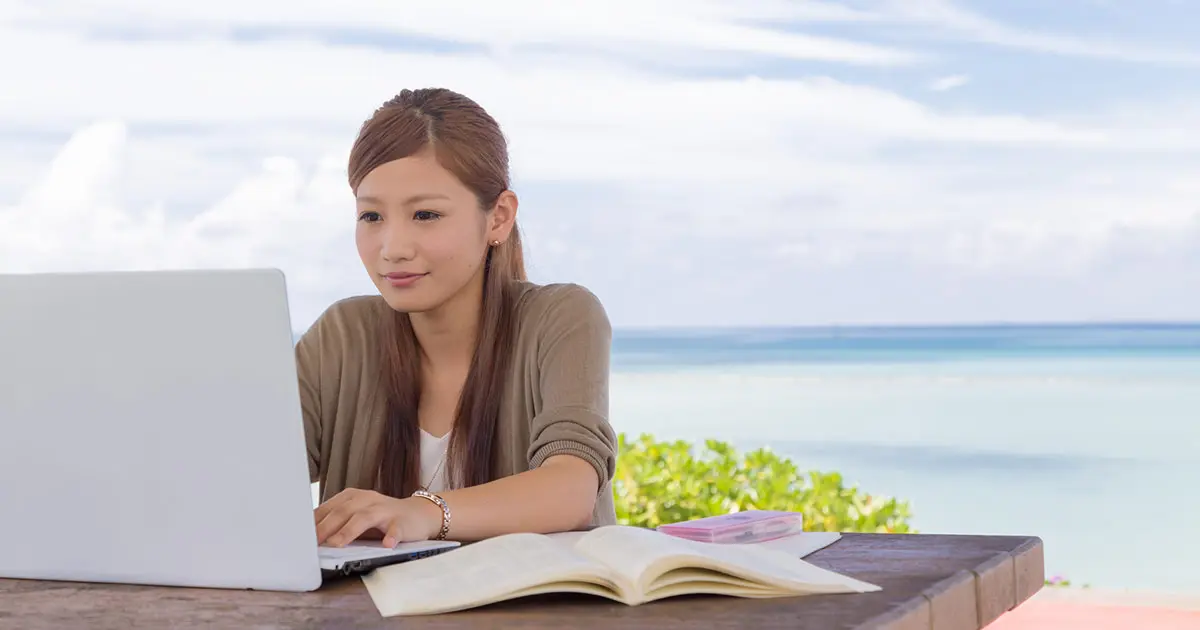まだ誤解してる?マイクロマネージメントの適切な運用と可能性

「マイクロマネージメント」と聞いて、どんな印象を持っていますか?
リープリーパーでは、刑務所の囚人を効率的・心理的に監視する「パノプティコン」と呼ばれる仕組みについて解説しました。抑圧的な監視体制からはイノベーションは起きないこと、そして信頼関係が重要だということを紹介しました。
従来、管理する側・される側双方にとってストレスフルだった古いマイクロマネージメントは、いわば「管理のための管理」。それが近年、IoTやスマートデバイス、AIの技術革新によってアップデートされています。管理する対象は、人の場合もあれば、デバイスや設備、環境の場合もあります。
今回から複数回にわたって、マイクロマネージメントの効果的な導入や注意点、IoTの先進的な取り組みなどについて、具体的な事例を交えながら紹介していきます。
マイクロマネージメントに対する先入観
マイクロマネージメントとは、管理者が部下の活動状況を逐一チェックし、細かく指示を出す管理手法のことを指します。これは、運用によって効果的な場合もあれば、業務を阻害することもあります。
そのため評価もさまざまですが、過度に干渉することで部下の自由度が低くなり、創造性が損なわれることから、ネガティブな管理手法の代表と見なされがちです。例えば、すべての作業にダブルチェックを要求されたり、文面やスライドの細部にクレームが入る、休憩時間が秒単位で計測される、タスクを過度に細分化して厳しい時間制限を設け、守らないと叱責される、などがあります。従業員にとっては、上司から細かくストーキングのように監視されることによるストレスなど、弊害の象徴として忌避されます。
一方の組織側にしてみれば、従業員の管理は業務の遂行に不可欠なこと。ただ、従業員を信頼せず、サボらずに働いているかを監視すること自体が一つの仕事になっていれば、DXの余裕など生まれません。過干渉は、教育現場や家庭でもたびたび問題となっています。
Amazon.co.jp: 他者と働く──「わかりあえなさ」から始める組織論 (NewsPicksパブリッシング) eBook : 宇田川元一: Kindleストア
しかし、マネージメント(管理)とは本来、仕事に限らず必要なことのはず。
例えば、その人のやり方や目標が間違っていれば、早めに修正を指示したり、より効果的なアプローチをアドバイスしたり、気付かない視点を指摘するのは管理者として必要なサポートです。また、管理される側にしても、貢献が正しく評価され、次のステップへと進む目標が提案されることには、大きな価値があります。
一方的な強制力を持ち、時に抑圧的な「コントロール」ではない、適切な「マネージメント」。これは本来、人のポジティブな面を引き出す大きな可能性を持っています。対象のことを細かく具体的に把握しておくのは、あくまでもその目的達成のための手段の一つに過ぎないはずです。
リモートワークでも問題視されたマイクロマネージメント
マイクロマネージメントは、同じ空間と時間を対面で共有できず、相手の詳細が把握できないコロナ禍で、改めて注目を集めました。リモートワークがある程度普及したアフターコロナの今、ビッグテックを中心とした企業の多くが出社に回帰したり、ハイブリッドなワークスタイルに移っています。
上司や同僚とリアルに対面する機会が減ると、コミュニケーションの解像度が下がる一方、不安感は増大しがちです。わざわざスケジュール登録するほどではない、ログに残らないちょっとしたやり取りができない。対面組とリモート組で、情報や信頼格差ができてしまう。ディスプレイ越しだと、どこで録音・録画・スクリーンショットが撮られているかわからない。不安を引き起こす原因もさまざまです。
▼出社してもすぐに帰宅「コーヒーバッジング」が広がる納得の理由:「出社×テレワーク」の実情【前編】 – TechTargetジャパン ERP
https://techtarget.itmedia.co.jp/tt/news/2412/11/news10.html
一方で、オンラインでほぼ完結するIT系の仕事では、リモートワークができることが就職・転職の必須条件という人も珍しくありません。対人接触が苦手なので、必要なときに画面越しのやり取りだけで済ませたいニーズも。
そもそも、地方では選べる仕事が限られ、都市部に比較すると賃金も低いため、リモートでも働けるオプションは、労働者にとっては魅力的です。また、子育てや介護、健康状態や障害など、それぞれの事情を考慮した条件さえクリアすれば労働力として活躍してくれる人材は、組織側にとっても貴重です。
監視と管理による迅速かつ具体的なサポートを求めているか、逆に疎ましく感じるかは、組織や人、状況によって違うのは当然です。個人ごとの違いや事情を考慮し、パフォーマンスを最大化するには、具体的な詳細を把握することが不可欠です。
効果を活かす!マイクロマネージメントのメリット
根強いマイナス・イメージを一旦軽くフラットにしたところで、マイクロマネージメントのメリットを冷静に観察してみましょう。
細部への注意が生む高い品質
マイクロマネージメントの最大の利点は、プロジェクトの細部にまで目を配ることで、品質を確保できる点です。特に、以下のような状況では有効です。
- 厳密な基準が必要なプロジェクト:医療機器や航空宇宙産業など、些細なミスが大きな危険を引き起こす現場では、リスクを最小限に抑制
- 新しいプロセスや未経験の分野:初めての状況では、詳細な指導やチェックを取り入れることで、未知の混乱やヒューマンエラーを回避
データ駆動型の意思決定
管理者は、取得されたデータに基づいた意思決定を下せます。過度な干渉を避けつつ、適切なサポートやリソースを提供することで、従業員も業務に対する理解や信頼感が生まれます。
- 業務の可視化による生産性向上:データに基づく業務改善で、ムダな時間を削減
- リアルタイムのフィードバック:従業員が業務を改善する具体的な指針を、迅速に提供
スキル育成の促進と支援
きめ細やかな管理を通じて、マネージャーは部下に対して直接的なフィードバックを提供できます。これは、特に新人や経験の浅いメンバーに効果があります(Z世代については、また後日の記事で)。
- 学習のスピードアップ:効果的なマニュアルと具体的な指導により、迅速にスキルを習得
- 即時的な修正と改善:その場でフィードバックを受けることで、成果物の精度が向上
健康管理とウェルビーイング
従業員の健康状態をモニターすることで、ストレスや疲労の兆候を早期に発見できます。これは、結果的に生産性の向上につながります。
- 健康状態をモニタリング:従業員のストレスや疲労を軽減し、高いパフォーマンスを実現
- スマートデバイスの導入:細かいデータで従業員を支援(これも次回以降の記事で)
チームの目標達成力向上
マイクロマネージメントは、個人単位だけでなく、チーム単位の目標達成にも直結。業務プロセスの最適化にも有効です。
- チームとしての一体感:細部まで指示が行き届き、全員が同じ目標に向かって効率的に稼働
- ケアレスミスの予防:単純ミスや問題の早期発見により、計画通りにプロジェクトを遂行
顧客満足度の向上
顧客対応においてもマイクロマネージメントは役立ち、より高い顧客満足度を達成できます。
- 高い基準を維持:顧客の要求に細かく対応することで、高い満足度を達成
- プロセスの透明性:詳細な報告とチェックにより、顧客からの信頼を獲得
緊急時や危機的状況での有効性
過去の事例を踏襲できないような状況では、迅速な意思決定と詳細な管理がリカバーの鍵になります。
- リーダーシップの強化:重要な場面で細かく指示を出すことで、混乱を最小限に
- リスク管理:予期せぬ問題に対処する際、細部へ注意を払うことでリスクを軽減
ガバナンスとリスク管理
勤務時間や実態を細かく監視するのであれば、同様に、業務には該当しない時間やタスクも管理が必須。長時間労働や情報漏洩など、ビジネス面のリスクを管理できます。
- コンプライアンス強化:労働時間や内容が適正に管理され、過重労働や不正を防止。
もちろん、冒頭で紹介したようなデメリットもあります。それらについては、拒絶反応がより強い傾向を示すZ世代の視点からチェックしてみます。後日公開予定の記事をお待ちください。
御社のマネージメントは、成功していますか?それとも課題があるでしょうか?ご意見・ご感想をぜひお聞かせください。
さて、細かなマネージメントの目的は、取得した具体的なデータを利用して、従業員の多様なニーズに応じた柔軟なサポートを可能にするためのはず。マクロで見ると、国や地域によっても違いがあるのも現実です。
しかしこれが今、危機に瀕しています。詳しくは、次回の記事へと続きます!


![マイクロマネジメントが仕事の効率を下げる理由 [2024]](https://assets.asana.biz/m/332c6c3044bf0cd4/webimage-Article-leadership-macromanagement-2x.jpg)