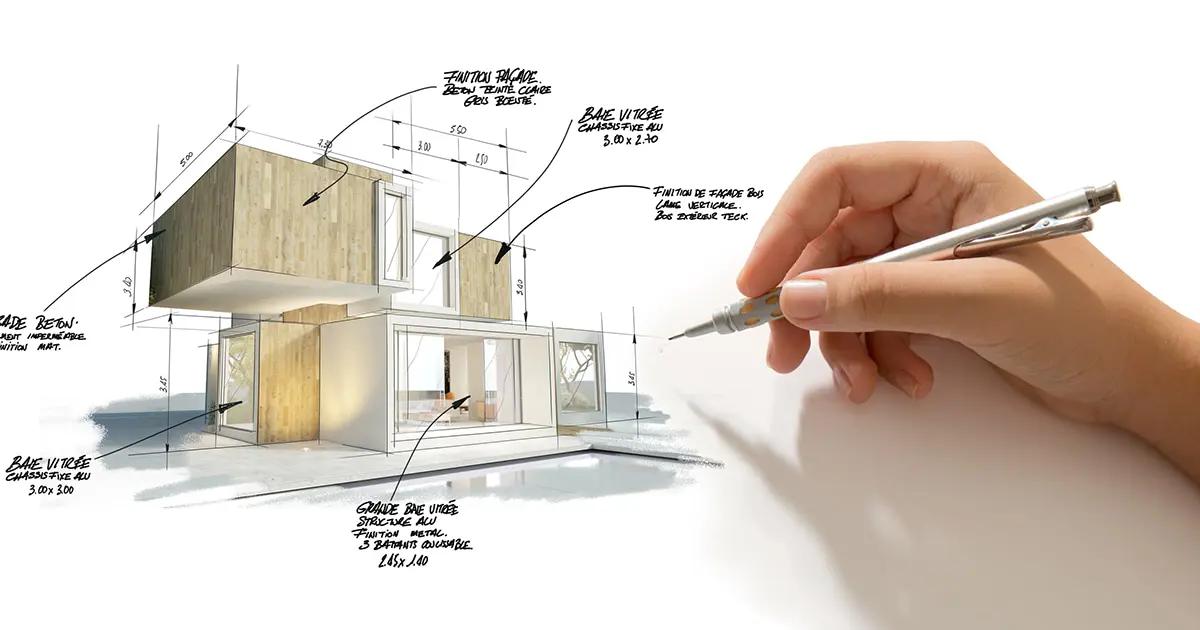どうなる?ESPR…ローコードで企業変革DXを推進するしかない理由

持続可能な社会を実現するための、製品の設計や製造、販売、物流、廃棄など、ライフサイクル全体を考慮した、EUのエコデザイン規制であるESPR。前回の記事では、その基本情報をチェックしました。EUでビジネス展開している企業でなくても、私たちが何らかの形で影響を受ける十分な理由があります。
今回は、先行きが読めないビジネス環境において「変化を利用する」ために、柔軟で効率的なローコード開発プラットフォームが果たす、重要な役割について考えてみましょう。
トランプ再選という巨大リスク
世界の貿易と環境に強い影響力を持つ国、アメリカ。その国民の半数以上が、環境危機や持続性・多様性より、目の前のインフレ対策への期待を選択しました。人種で括るというより、性差や世代間格差も大きいことが顕著になりました。保護主義的な自国最優先路線を貫くことは明白です。
また、移民問題はEUでも深刻で、極右勢力が躍進しています。さらにEUにとっては、気候変動対策のパリ協定からアメリカが離脱することが決定的になったことや、ロシアのさらなる軍事侵攻という懸念が現実になりつつあります。
ESPRは、EUの規制としてGDPR(EU一般データ保護規則)を運用してきたように、独自路線を貫いて対決姿勢を示す選択もあるでしょう。逆に、落としどころを探る中で、骨抜きになってしまう可能性もあります。
とにかく、2025年1月の就任以降、どのように状況が変わるかは全く予断を許しません。
EU域内だけでなく国際協調が不可欠
トランプ政権がどういう態度に出るかに関わらず、ESPRの持続可能な社会と経済成長の両立という理想は、業界団体や地方自治体、国レベルでの実行力を伴ったルール作りや法整備が不可欠です。実現に向けては、各国の状況や国際情勢を踏まえた、より厳しい対応や調整が必要になりそうです。
国際貿易への影響
世界各地で保護主義的な政策が台頭し、グローバルサプライチェーンの再編も進んでいます。WTO(世界貿易機関)が定めるルールとの整合性も必要です。
地政学的な課題
EUはこれから厳しい冬に差し掛かります。ウクライナ情勢では、ロシアの天然ガスが大きなリスク要因となりました。環境規制とエネルギー政策は各国で温度差があり、国際協調の難しさが浮き彫りになります。
想定される対応策
持続可能性ある手法を導入するには、産業界全体で対話を重ねながら進める段階的なアプローチが必須です。導入に向けて、インセンティブやイノベーションを促進する必要も。二国間・多国間協定や国際協力を強化することも不可欠です。
実務的な課題
細かいトレーサビリティーに掛かるコストは、商品やサービス価格に転嫁せざるを得ません。しかし、企業にとっては、市場での競争力を犠牲にしてまで達成することは非現実的。柔軟な最適化が求められます。
柔軟なITシステム
デジタル製品パスポート(DPP)の導入と管理や、国境を越えたサプライチェーン全体での情報連携など、製品ライフサイクル全般でのデータトラッキングが必須に。柔軟で拡張性の高いITシステムの構築と人材育成は必須です。
予測不可能な不安を踏まえた、未来の機会
BANIという言葉で象徴される、理解不能で不確実な、不安に満ちた世相を、今ほどリアルに感じられることもないかもしれません。ESPRの実際の規制や規則の内容、実現可能性、マーケットの変化などは全く読めません。しかし、未知の規制への対応は、消極的・場当たり的な措置ではなく、企業の競争力強化とイノベーション創出のチャンスでもあります。
規制対応を戦略的機会として捉える
- ビジネスプロセスの最適化・効率化
- コンプライアンス対応に留まらない価値創出
- グローバル競争力の強化
持続可能な変革の実現
- 段階的なアプローチによるリスク低減
- 組織能力の継続的な向上
- イノベーション文化の醸成
予測不能なESPRに対して、いつ、何をすべきか?
EUでビジネスを展開していない日本企業にも、何らかの形で影響がある以上、政府組織や業界団体、EU当局などが発表する情報は、定期的に収集しておきましょう。セミナーやレポートで、先行企業の事例の研究や、規制動向の変化に対応する調査も有効です。
できるだけ早期
- 影響範囲の特定と評価:対象となる製品やサービスの洗い出し、サプライチェーンの現実、現行の環境対応状況の確認など。
- ステークホルダーとの協調:環境配慮型製品への理解を顧客に直接訴求。修理方法や耐久性、リサイクル、廃棄に関する情報と具体的手法を充実。
- 社内体制の整備:担当部署ごとに責任者を決定、情報収集体制を構築。関連部門間で連携を強化したり、勉強会で危機感とノウハウを共有。
- ローコード開発環境の整備:テストプロジェクトを実施し、評価する。初期の人材育成プログラムもスタートさせる。
中期的な準備(1〜2年)
- 製品設計の見直し:修理しやすい、モジュール化した設計に。リサイクル可能な材料を積極的に採用。
- 柔軟なシステムを開発:トレーサビリティーを実現できるシステム開発の内製化。データ管理体制の整備を進め、デジタルパスポート対応を準備。
- ローコード技術者の育成:DX人材としてのローコードエンジニアを社内で育成し、どのように状況の変化にも対応できる社内外の体制を築く。
- 修理・メンテナンスの習慣化:製品を長く使うことを前提とした選択を、ユーザーに訴求する。単なる販売ではなく、環境負荷に役立つ情報を提供する。
長期的な取り組み
- ビジネスモデルの転換:サービス化(Product as a Service)や循環型ビジネスへの移行を含め、新規事業のチャンスを模索する。
- イノベーションの促進:新たな製品設計・製造手法を確立する。環境配慮型テクノロジーを開発したり、代替材料の研究を進める。
- デジタルレイバーの実現:AIや自動化技術による仮想労働者と協働し、レジリエンス(回復性)を高めておく。
- 社会の変化に対応:シェアリングサービスの活用や、環境影響を考慮した生活様式の確立など、消費習慣のアップデートにも柔軟に対応する。
変化に強いローコード開発による攻めのDX
企業ができる対策としては、柔軟かつ効率的なITシステムによって、自社ビジネスのアジリティー(俊敏性)とレジリエンス(回復性)を高めるしかありません。その時、ローコード開発プラットフォームという選択肢が、積極的な変革を実現する有効な手段として、心強い味方となるはずです。
社内で内製化できる体制を整えるために、ローコード開発を導入し、段階的なアプローチを進めることが、最短かつ最適な解決策です。
ローコード開発の戦略的活用
- 内製化による効率化・高速化
- アジャイルなサイクルによるトライ&エラー
- 柔軟性とスケーラビリティーの確保
- 開発運用のコストダウンと最適化
持続可能な人材育成
- 非エンジニアをシチズンデベロッパーに
- DX人材としてのローコードエンジニア育成
- クロスファンクショナルなチーム編成
- 継続的な技術トレーニングの実施
ナレッジマネジメント
- 属人化しがちな暗黙知の形式知化
- ベストプラクティスの共有
- デジタルナレッジベースの構築
- チームのコラボレーション促進
結局、起きる変化をどう「使う」か?
ESG(環境、社会、ガバナンス)やSDGs(持続可能な社会のためのゴール)は、重要ではあるものの、数年前からの「ブーム」が一段落した今、ただの綺麗事だと扱う向きもあります。それらを掲げる企業が実際に取り組んでいるかどうかに関わらず、例えば就活セミナーで企業が学生にアピールしたところで、特に目新しさはなく、他企業との差別化にもなりません。
今後のアメリカの政策により、想定を上回る事態が起きる可能性は、2016年の比ではありません。ESPRは、今すぐ自社に影響することはなくても、同じ理念を持つ規制は何れ求められます。とにかく、起きることが確実な大きな変化は、それがどんな内容であっても避けることができません。
重要なポイントは、起きる変化を上手く「使う」方法を模索すること。「規制強化への対応」としてではなく、新たなビジネスチャンスやイノベーションとして、自社が有利になるように利用する視点が不可欠です。
予測不能なビジネス環境において、企業の持続的な成長を実現するには、柔軟なシステム基盤と強固な組織能力が大前提。ローコード開発を軸としたDX推進は、この課題に対する有効な解決策の一つとなります。組織全体のDX変革を推進し、より強靭で競争力のある企業へと進化することが、今後の変化に強い戦略的な選択となるでしょう。その意味では、ESPRは一つの契機に過ぎません。
そのためには、意思決定速度を上げ、小さな失敗や変更を繰り返すアジャイルなアプローチがカギ。現状のビジネスからスムーズに移行させたり、競合に対する優位性を確保するために、2025年1月を待たず、今すぐできる準備をスタートさせましょう!