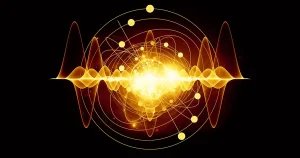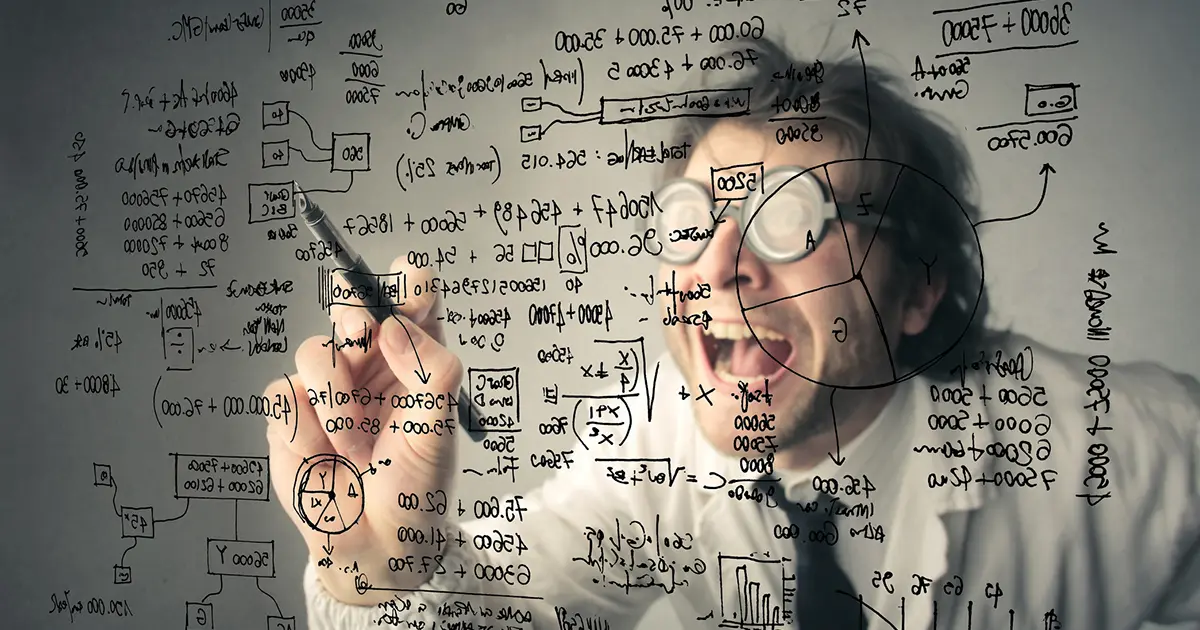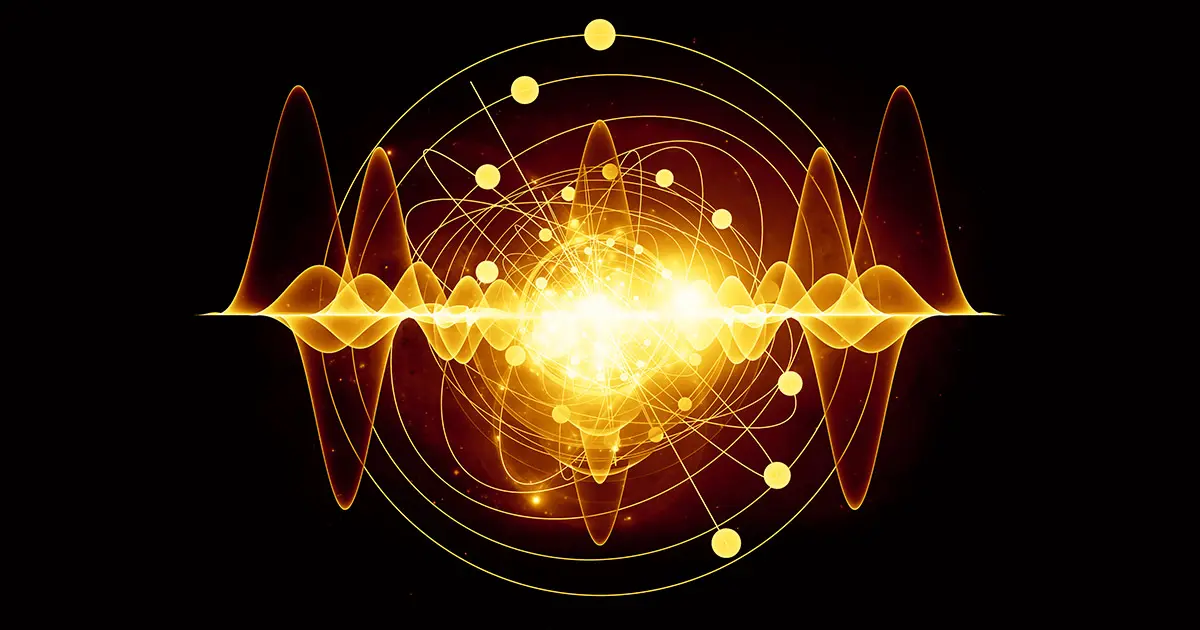イジングモデル型量子コンピューター1:量子と量子力学とは

今回と次回の2回に分けて、「イジングモデル型」量子コンピューターの基礎について説明します。今回の記事では、量子コンピューターの基本を解説します。動作原理というよりも、基盤となる量子力学の基本概念を中心に進めていきます。まずは、「量子とは何か?」「量子力学とはどのような分野なのか?」を理解するところから始めましょう。
極小世界を探求する「量子力学」とは?
「量子力学」とは、非常に小さな世界(原子よりも小さいスケール)における物体の振る舞いを研究する物理学の一分野です。一般に「力学」とは、物体の運動を記述する分野を指し、その基礎はアイザック・ニュートン(1642–1727)によって完成されたと考えられていました。
ニュートンは、運動3法則(慣性の法則、運動の法則、作用・反作用の法則)を示しました。ニュートン力学では、例えば3つの物体が万有引力で引き合う場合の運動(いわゆる三体問題)を、理論的にはニュートンの運動の3法則を用いて解けるとされていました。
しかし、科学が進展する中で、「極大の世界」と「極小の世界」では、ニュートン力学が適用できない領域が存在することが明らかになりました。非常に大きい世界の力学を記述するのがアインシュタインの相対性理論であり、非常に小さい世界の力学を記述するのが量子力学です。
ニュートン力学と現代物理学の関係
では、ニュートン力学は完全に誤りだったのか?というとそうではありません。相対性理論や量子力学においても、日常スケールでの現象を近似すると、ニュートンの運動方程式に帰着することが知られています。このため、ニュートン力学は依然として有効であり、現代物理学の基盤の一部をなしています。
しかし、極大の世界を扱う相対性理論と極小の世界を扱う量子力学は、現時点では統一されていません。この統一を目指す研究は、現代物理学の最先端の課題のひとつとなっています。
量子の特徴:不連続性と重ね合わせ
量子力学における原子や電子といった微小な物体は、私たちの日常感覚では想像できない、奇妙な振る舞いをします。特に、量子コンピューターに関連する、次の2つの重要な性質を持っています。
量子の状態は不連続的である
量子の状態は重ね合わさっている
量子の不連続性
「量子の状態が不連続である」とは、「量子は特定の状態しか取れず、特定の状態の間で連続的に変化できない」という意味です。
分かりやすく説明するために、人工衛星の軌道を例に考えてみましょう。地球の周りには、膨大な人工衛星や宇宙ステーションがあります。地球を周回する人工衛星は、高度を連続的に変化させることが可能です。
一方、量子力学の世界では、電子が原子核の周囲を回る軌道は特定の値しか取れません。つまり、電子は自由に軌道を変えることができず、決まった軌道間を飛び続けるしかないのです。
花火に応用される電子のエネルギー
電子が特定の軌道しか取らないという性質により、電子のエネルギーも特定の値に限定されます。このため、電子が軌道を移る際には常に一定のエネルギーが放出され、それが光として観測されます。
この現象は炎色反応として知られ、銅なら緑、ナトリウムなら黄、カルシウムなら赤に光ります。花火が鮮やかな色を放つのは、この性質を利用しているからです。
量子の重ね合わせ
「量子の重ね合わせ」状態とは、1つの量子が複数の状態を同時に持つことを意味します。こちらも、前例に続けてみましょう。
例えば、人工衛星は地球を周回していますが、その回っている軌道はある平面内に存在します。しかし、原子内の電子の位置は、原子核を中心に立体的に広がります。さまざまな周回軌道が同時に存在し、観測した瞬間に1つに定まります。観測する瞬間までどの軌道になっているのか分からないのではなく、複数回観測すると、電子は常に異なる位置に現れ、特定の平面には収まりません。これが量子の重ね合わせという現象です。
「シュレディンガーの猫」:量子の重ね合わせを示す思考実験
「観測するまで状態が確定しない」量子の重ね合わせを、直感的に理解するための有名な思考実験が、「シュレディンガーの猫」です。これは、オーストリアの物理学者エルヴィン・シュレディンガー(1887–1961)の提唱した実験で、以下のような手順で実施されます。
- 箱の中にネコを入れる
- 1時間以内に50%の確率で崩壊する放射性原子を用意する
- 放射線を検出すると作動するハンマーをセットする
- ハンマーが瓶を割ると毒ガスを発生させる仕組みにする
- 箱の蓋を閉じ、中の様子を見えなくする

箱を密閉するので中の様子は見えませんが、次の2つの可能性が同時に存在します。
- 原子核が崩壊しない → 何も起こらずネコは生存
- 原子核が崩壊して放射線が出る → ハンマーが瓶を割って毒ガスが発生→ ネコは死亡
箱を開けて観測するまで、ネコは「生きている」と「死んでいる」の状態が重ね合わさっていると解釈されます。このような現象が、量子の重ね合わせを象徴的に説明する例としてよく用いられます。
この「シュレディンガーの猫」を引き合いに出して、「観測するまで分からない」という主張がたまに見られますが、「観測するまで両方が同時に存在している」というのが正しい理解です。一般には理解しがたいかもしれませんが、箱の中の猫は「生きているし、死んでもいる」のです。
「量子もつれ」と量子コンピューターの高速化
量子コンピューターが特定の問題に対して、古典コンピューター(従来型・現行のコンピューター)よりも高速に解を得られる、という主張があります。その理由の1つに、「量子もつれ」という現象があります。
元々、古典コンピューターは、問題を解くのにどうしても総当たりをしなければなりません。これに対して、量子コンピューターでは、2つ以上の量子が相互作用によって強く関連し合い、片方を観測するともう片方の状態が瞬時に確定する現象である、量子もつれを応用できます。
コンピューターの最小単位は1 bitであり、これは0と1の2つの状態を表しています。例えば、2つの量子がもつれている場合、どちらの量子も同じ状態(0であり、同時に1でもある)を取るようになります。この性質を利用すると、計算の確率を操作して特定の結果が出やすくなり、古典コンピューターよりも効率的に問題を解けるのです。

量子同士を相互作用させ、確率を高める量子コンピューター
ただ、量子を2つ用意したところで、その量子が独立している場合は、それぞれがランダムな結果を返すだけです。おみくじには使えるかも知れませんが、それでは計算機としては使えません。量子同士を相互作用させることで、量子が同じ値になる状態を作り出せるのです。
50%の確率で0と1のどちらかになる、2つの量子が独立して存在する場合で考えると、観測結果は「0と0」「0と1」「1と0」」「1と1」の4パターンが考えられます。しかし量子がもつれ、2つの量子が同じ数字にしかならない状態を作り出すと、「0と0」または「1と1」の2つのパターンしか存在し得なくなります。もちろんこの2つも、どちらになるかは確率的に決まります。しかし、独立している場合は各パターンが25%ずつしか登場しない結果が、量子をもつれさせると特定のパターンは0%、もう一方の特定のパターンは50%と確率が変動します。量子コンピューターのソフトウェア面では、これを利用して高速な計算が実現できないかを考えています。
ここで重要なのは、量子コンピューターが高速計算を実現できるのは、その確率を量子もつれによって変動させられるからという点です。
古典コンピューターと違って、一度の計算で完全な結果を得られるわけではありません。複数回、高速計算して最も高い頻度で出現する結果を採用します。確率的であるため、計算をし直すと答が変わることがあります。単なる確率的な計算では、古典コンピューターと同程度の速度しか得られませんが、量子もつれによって特定の確率を高められるため、計算回数を大幅に削減できるのです。
次回の記事では、イジングモデル型量子コンピューターにおける「スピン」とエネルギーの関係について詳しく解説します。また、「量子アニーリング」による最適化問題の解法についても触れますので、お楽しみに。