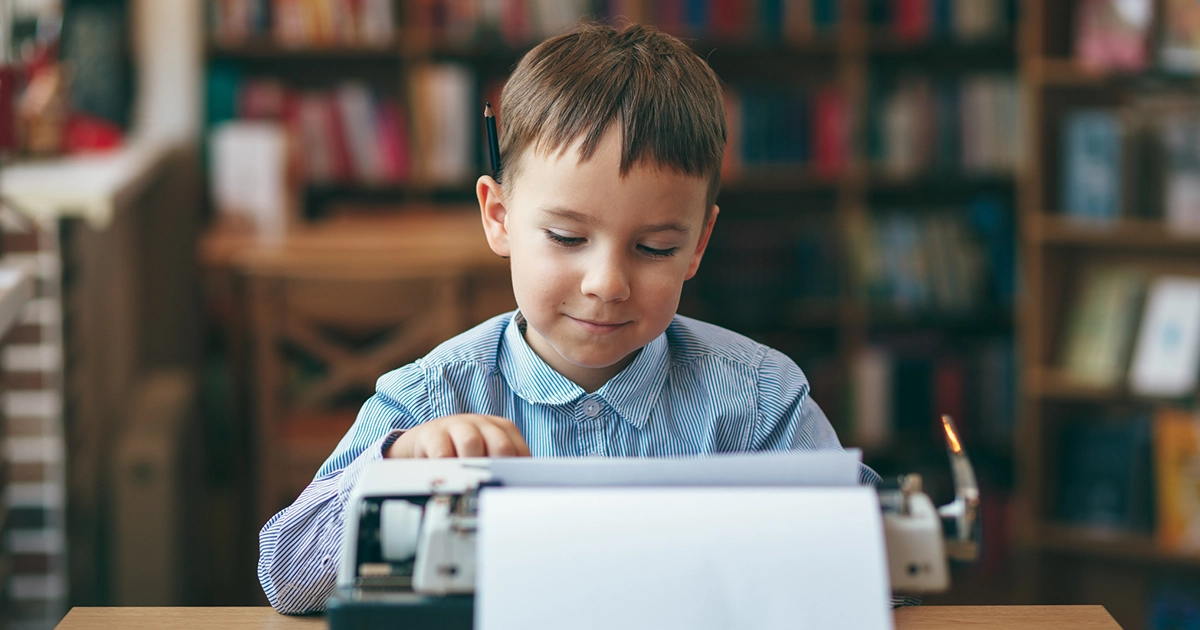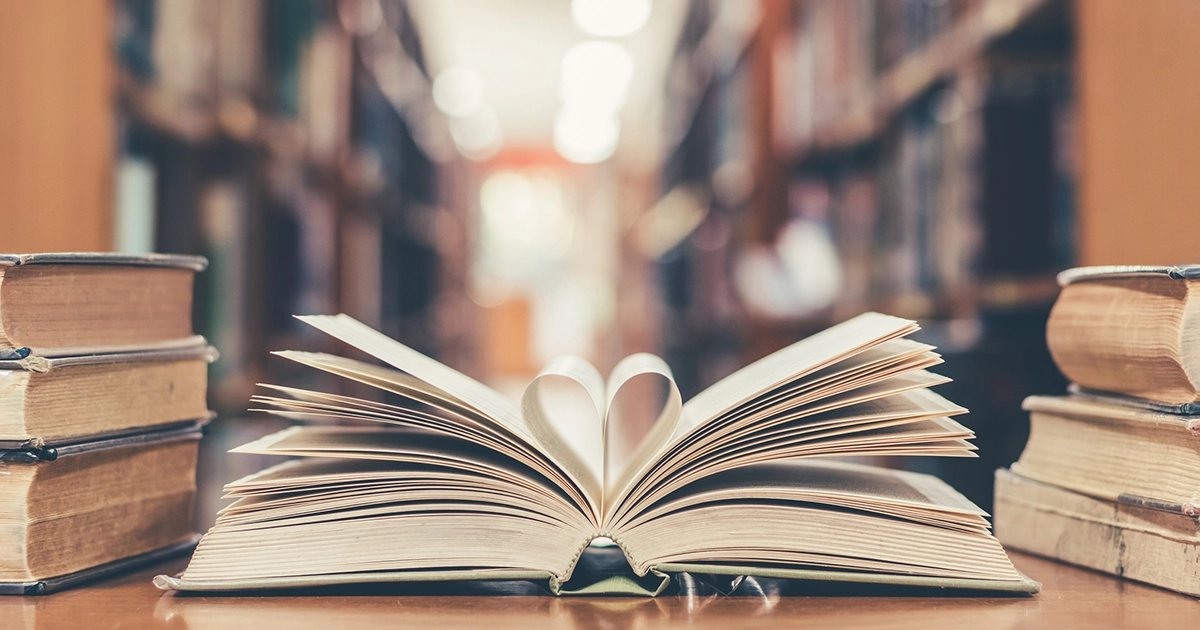こうして物語は失敗する!あなたのナラティブが聞き手に届かない訳

2020年頃から流行し熱狂的な支持を集めたのが、ナラティブという言葉とそのアプローチ。前回の記事では、成功した企業を紹介しましたが、真の成功は企業の中核的価値観や行動とナラティブを一致させることから生まれます。
しかし、すべての物語がハッピーエンドで終わらないのと同様に、必ずしもナラティブが機能するとは限りません。今回は、ナラティブが失敗する原因にフォーカスしてみます。前回の記事からお読みいただければ幸いです。
ナラティブなアプローチが上手くいかない原因
ナラティブの特徴を活かせばコミュニケーションに有効なはずが、なぜ失敗するのか?ありがちな原因を探ってみましょう。
主語が自社や特定の主人公
ナラティブの主役は、ステークホルダーである「私(たち)、あなた(たち)」で、特定の組織や主人公ではありません。聴衆にとって自分事化されない限り、ナラティブの本質を活かすことはできません。
広告やマーケの一つだと誤解
ナラティブを、広告手法やマーケティングツールの一つだと誤解すれば、効果がないどころか反発を招くリスクがあります。自社製品について自分で語るのは単なる広告に過ぎず、幅広い共感や支持は得られません。
実質よりも「物語」への偏重
魅力的な物語が、真の成功につながるわけではありません。根本的な社会課題に取り組むことがなければ、消費されるだけで終わってしまいます。何より、ナラティブの物語はコントロールが不可能です。
信憑性や整合性の欠落
相手が経営層なら、物語に添えて具体的な数値を端的に示すのは有効かつ必要です。しかし、事実とは異なる「盛った」演出は逆効果。化けの皮が剥がれてしまえば、聴衆は懐疑的になり、離反して二度と戻ってきません。
短期的話題性を狙ってしまう
バズっても、それだけ?終わりのない物語としてのナラティブを良好に構築するには、持続的な努力と関与が不可欠です。一貫した行動と価値創造がなければ、長期的な成長に結びつくはずがありません。
激変する外部要因の変化と影響
新型コロナウイルスや国際情勢の緊迫、生成AIの普及、市場競争や変化など、ビジネス環境は複雑です。避けがたい外部要因を考慮せずに、全ての成功や失敗の要因をナラティブに帰するのは非現実的です。
誰が、何を、どのようにストーリーを語るか?
物語は、語り手や聴衆との関係、構成、要素などが変われば、ストーリーテリングにもナラティブにもなります。組織の成功物語や個人の愛憎劇から、社会課題の解決まで、幅広い可能性が生まれます。ただし、この両者は扱いが大きく異なります。
例えば、こういう構成要素がある時、ストーリーテリングなら…
ストーリーテリングの構成要素
- タイトル:社名や商品・サービス名、人物名入り
- テーマ:観客の心に響く根本的なメッセージや意味、物語全体を通じて達成されるべきこと
- キャラクター:観客が感情移入し、応援したくなるような人物(または何か)
- 設定:出来事が展開される時間や場所、雰囲気、環境、時代、バックグラウンドなどの条件
- プロット(あらすじ):物語を前進させ、緊張を高め、解決へと導く一連の出来事
- コンフリクト(対立や闘争):緊張感を生み出し、キャラクターの旅を後押しする障害や挑戦
会社をメインにすれば社史や企業紹介になり、さまざまな試練が襲いかかる人物を主人公にすれば、聴衆が感情移入しやすくなります。個人を取り上げるのも、会社説明や人材募集ではよくある演出。新しい商品やサービスによって、課題が解決したりチャンスが拡がれば、組織の発展を示すストーリーにピッタリ。製品の高い評価やトラブルに対して果たした役割を入れると、従業員の誇りや自尊心を喚起できます。また、製品の不具合発覚や工房との衝突、ライバル企業との鬩ぎ合いなどのエピソードを散りばめれば、緊張感を高め、物語にリズムが生まれます。そして、社名やブランド名が添えられた完成済みの物語として、パッケージ化されアウトプットされます。
ナラティブを醸成するために、組織がすべきこと
一方、ナラティブでは、ステークホルダーである「あなた」に語ってもらうことが必須です。対話を醸成していくには、自分たちの製品や技術、業界を主語にしてはいけません(それはストーリーテリング)。常に変化し続けるのであらすじなどは無く、キャラクターや設定、闘争の対象も常に変わっていきます。
では、組織としてできることはないのでは?いえ、コントロールはできませんが、マネージメントは可能です。
ナラティブの構成要素
- タイトル:ナラティブを象徴する短めの文章(ハッシュタグとして伝わるほどの)
- 対象範囲:自社全体か?特定の商品やサービスか?
- 社会問題:自社に関係すること・関与できそうなことで、何が社会で問題となっているか?
- 存在意義:社会問題を解決するために何ができるか?提供できる価値と、存在意義とは?
- 関係と将来像:問題が解決された、未来のステークホルダーが抱く感情や感想は?
- 設定:これらの設定はあくまで社内に留めておき、公開する必要はない
まず、考え方・取り組み方を検討する上で、対象となるのが自社全体なのか、特定の商品やサービスブランドなのかを判断しましょう。次に、何が問題なのか、社会課題を認知します。この両者は密接に関係していて、課題の種類や大きさ、組織の立場によってさまざまです。
例えば、働く女性が感じているジェンダー的抑圧や、育児や介護と仕事の両立は、自社の商品やサービスだけでなく、社内で抱える問題ともリンクすることもあり得ます。一方、二酸化炭素排出量の削減や、DX人材の育成は、直接は関係しなかったり、課題が大きすぎるかもしれません。また、一つの自社製品に関する投稿をソーシャルメディアのエゴサーチで発見し、それをきっかけに社内で検討を重ねた結果、全社で取り組むべき課題にまでエスカレーションすることも十分あり得ます。
社会問題と自社の関わりが把握できたら、自社の商品やサービスを通じて、どのように問題を解決できるのか?を考えます。「語り手ではない第三者」として自社が、本業を通じてできる価値提供とは何なのか?いろいろな側面から、意見交換を繰り返していきます。ナラティブでは、全てをお膳立てすることはできず、コミュニティーとしてのオーディエンスとのコラボレーションが鍵です。
そして最後に、問題が解決されたステークホルダーの将来像について考えます。ナラティブには終わりがなく、物語は次々と変化していくので、将来も想像や仮定でしかありません。しかし、カスタマージャーニーのように一つの旅を体験し終えた人物が、どのように幸福な状態になっているか、できるだけ具体的にイメージすることは有効です。
注意しておくべきは、これらのナラティブの設定は、ストーリーテリングと違って表には出ないことです。これらはあくまでも、自社がナラティブに関与する上での考え方をまとめた指針であり、社外に示すためのものではありません。
パーパスやミッション、ビジョン、バリュー、クレドとの関係は?
社会にとっての、自社の存在価値やステークホルダーとの約束、目指す方向を考え直す上で不可欠なのが、パーパスやミッション、ビジョン、バリュー、クレドなどです。これらも、ナラティブに深く関係する要素なので、整理しておきましょう。
これらはどれも、ビジネスコミュニケーション戦略における不可欠な要素で、相互に関連しています。意識や明文化をしている・いないに関係なく、優れた企業にはこれらが間違いなく存在します。そして、力強いナラティブが、これら自社の存在価値や将来像、使命感、価値観などを効果的に伝える、重要な役割を果たしているのです。
- パーパス(目的):「パーパス経営」という概念もよく見聞きしますが、これは根本的な自社の目的であり、存在意義です。パーパスは、ナラティブとして語られる物語の起点となり、短くシンプルなステートメント(宣言)として表現されます。
- ミッション(使命):中核となる活動や目標を簡潔にまとめたメッセージです。ナラティブは、ミッションの達成に向けた道のりを描写しますが、ミッションはその中で具体的に「何をするのか」に焦点が当てられています。
- ビジョン:未来志向のステートメントで、目指すべき姿や将来像を表します。ビジョンとして描かれた理想の未来の中で、ステークホルダーがどのような言動をしているか、ナラティブで具体的に想像します。
- バリュー(価値):顧客に示すビジネスの価値や有用性・重要性です。ナラティブは、その価値がステークホルダーに具体的にどのような利益をもたらすか、効果的に伝える役割を果たします。
- クレド(信条):組織内部に示す、ビジネス上の意思決定や交流の指針となる価値観や信条、倫理的・文化的原則です。ナラティブは、これらの価値観が現実の世界でどのように実践されているかを、物語として示します。
企業がナラティブについて考える場合、広告のように利用したり制御する意識を真っ先に捨てる必要があるでしょう。ストーリーテリングでは当たり前のことが、ナラティブでは通用しません。「何をすべきか」も重要ですが、「何をすべきではないか」が成否の鍵を握ります。
さて、次回は、「物語 vs 物語」のナラティブバトルとも言える現代の惨状を踏まえ、それでも希望ある物語を紡ぐために私たちがすべきことについて、さらに考えてみましょう。